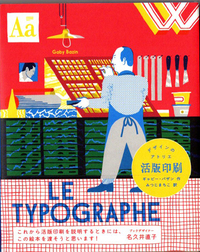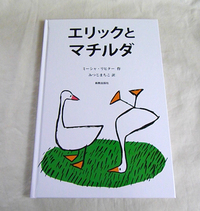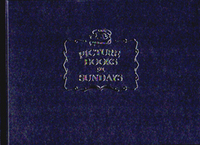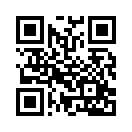本
世界はまるい
私なりの感想を書かせて頂きます。

世界はまるい
ガードルード・スタイン文
クメント・ハード 絵
マーガレット・ワイズ・ブラウン 編集
みつじまちこ 訳
アノニマ・スタジオ 出版社
この本には、子供だけでは無く、大人も楽しめる内容が書かれており、
「ウィーリーと歌」では、「パンをもってきて、バターをもってきて、チーズをもってきて、それにジャムをもってきて、
ミルクをもってきて、それにチキンをもってきて、たまごをもってきて、それからハムもすこしね。」
のような言葉遊び的に続く文章の楽しさがあり、
そして、「イスをもって山にのぼる」での、主人公のローズが青い椅子を抱えながら、山を登るシーンは、
一つの事を成し遂げようとする人間の姿を描いているようにも感じました。
1939年のアメリカの生活の中では、当時の児童書などにも多く見られるように、
第1章の「ローズはバラの花」に書かれている世界についての文章などでも感じるように、
宗教的な意味合いも含んでいるような気がしますが、
クリスチャンの人達が理想の場所(生き方や目標)的な意味合いで口にする「プロミスランド(約束の地)」が思い浮かび、
それを達成しようとするローズの姿は、プロミスランドを目指しているように感じます。
山の頂上に登って青い椅子に座ったら、そこから見える景色はきっと綺麗だろう。
それだけを目的に椅子を抱えて山を登る事は、自分に重荷を背負わせながら、理想の地を目指しているように感じます。
これは何かの困難を克服しながら、自分の目的を達成する事を描いているような気がします。
プロミスランド(約束の地)は、簡単にはたどり着く事が出来ない。様々な困難を克服し、
最終的にそこにたどり着く事が出来る。そして、そこにたどり着くまでに出会う様々な出来事が人間を成長させる。
たどり着く事はもちろん大切ですが、そこまでの経験から学ぶ事が重要なのかも知れません。
この本の中には、人間の成長や努力、経験など、生きていく為に学ばなくてはいけない多くの事が描かれている様な気がします。
昔、アメリカ人でクリスチャンの知り合いに「プロミスランド(約束の地)って何だ? と質問した時に、
「約束の地は、それぞれの人間によって違う。」という答えが返って来たのを思い出します。
たどり着く事が出来なければ、人生の終わりまで探し続けるのかも知れない。
人間はただ生活し、生きて行くだけではなく、何かの目的意識を持ち、それを達成する為に日々努力する事が大切だと感じます。
現代の複雑な社会生活の中で人間が暮らして行く為には、ただ、食べて生きて行く事だけではなく、
もっと他の何かが必要になって来る。その一つがプロミスランド(約束の地)を目指す事なのかも知れないと思います。
絵本を読み終えた後の答えは、人それぞれによって違い、答えは一つだけではないと思います。
答えは自由であり、違う答えが沢山あるはずです。子供が読んでも、大人が読んでも、新しい発見が古い本の中にはある。
そんな自由な発想が大人になっても必要ではないでしょうか?
また、本の最後に「世界のあるところでこの本を読んだあなたへ」で書かれている「世界はまるい」ができるまでという文章の中には、
この本がどのようにして作られたか、など、時代背景も含めて書かれており、この本が出版された理由を感じます。
そして、最後の文章の中には、同じタイトルの本が、3度違うイラストで出版されている事が書かれていますが、
これも、時代背景を考えて、イラストを描いているクレメント・ハードが、その時代に合ったイラストを意識して描いていると思われます。
実力のあるイラストレーターは、いろいろなイラストを描き表現する事が出来る。
クレメント・ハードも、そんな素晴らしいイラストレーターの一人だと感じます。
このような本を、この時代の日本で出版してくれた事に感謝します。
そして、この本が最初に出版された時代背景を追いながら、時代を遡って昔のアメリカを感じながら読んで貰えたら、
この本の制作に携わった人達も喜んで貰えるのではないでしょうか。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。